東京・鎌倉・駿河の旅 小田原・熱海篇 2016/4/1
|
小田原城は戦国時代から江戸時代にかけての日本の城(平山城)で、北条氏の本拠地として有名である。 |
|
 |
|
| 小田原城 | |
 |
 |
| 常盤木橋の桜 |
常盤木門前の階段 |
 |
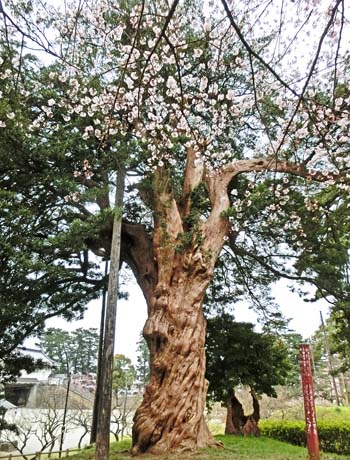 |
| 天守閣 | |
 |
|
| 住吉橋 |
イヌマキと桜 |
 |
 |
| 常盤木門 |
|
 |
 |
| 銅門(あかがねもん) |
|
|
|
|
 |
|
| 寛一お宮の像(車窓) | |
 |
 |
| お宮の松(お宮緑地)(車窓) |
初代お宮の松(お宮緑地)(車窓) |
 |
 |
| ?のオブジェ(お宮緑地)(車窓) |
熱海城(車窓) |
 |
 |
| 魚見崎(ホテルロイヤルウィングより) | 初島(ホテルロイヤルウィングより) |