奈良県を巡る旅 興福寺・春日大社篇 2017/4/15
|
いよいよ奈良県を巡る旅も今日が最終日。天気は残念ながら曇り空で午後にはにわか雨も降るとの予想で、何とか最後まで持ってくれないかと思っていた。 |
|
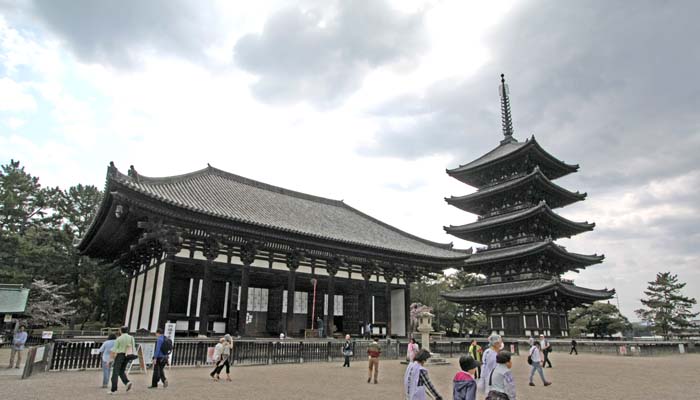 |
|
| 東金堂(とうこんどう) 五重塔 | |
 |
 |
| 南円堂 | |
 |
|
| 五重塔 | 鐘楼 |
 |
 |
| 猿沢池 | 北円堂 |
 |
|
| 三重塔 | |

|

|
| 大湯屋 | 本坊 |

|

|
|
花之松ノ碑 |
会津八一歌碑 |
|
|
|
 |
|
| 春日大社 南門 | |

|

|
| 二の鳥居 | 表参道 |

|

|
| 榎本神社 | 幣殿・舞殿(へいでん・ぶでん) |

|
 |
| 砂ずりの藤 |
椿本(つばきもと)神社 |

|

|
|
内侍門(ないしもん) |
総宮神社(そうぐうじんじゃ) |

|

|
| 水谷神社(みずやじんじゃ) |
水谷橋 |