東尋坊・永平寺・奥能登を巡る旅 金沢・八尾篇
2015/09/01
|
北陸新幹線が開通したこともあって越中八尾の「おわら風の盆」を見にやってきた。
|
|
|
|
|
|
北陸新幹線かがやき509号(W7系)大宮駅 |
|
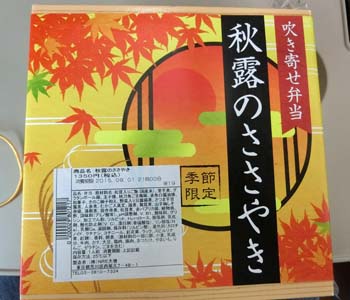 |
 |
|
吹き寄せ弁当〜秋露のささやき〜 |
|
|
|
|
|
鼓門(つづみもん) |
|
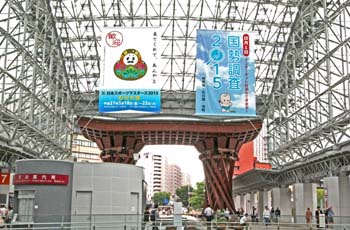 |
 |
|
もてなしドーム |
金沢駅前 |
|
|
|
|
|
|
東茶屋街(東方面望む) |
|
 |
|
|
東茶屋街(西方面望む) |
|
 |
 |
|
志摩(国重要文化財指定) |
旧かみや主屋・土蔵(金沢市指定文化財) |
 |
 |
|
黄金の蔵(箔座ひかり藏) |
|
|
|
 |
|
東茶屋街 |
杉玉(ひがしやま酒楽) |
 |
 |
|
菅原神社 |
宇多須神社(うたすじんじゃ) |
|
|
 |
|
東茶屋街 |
|
 |
 |
|
くずきり(森八茶寮) |
旧中屋 |
 |
 |
|
東茶屋街 |
|
|
|
 |
|
円長寺 |
四万六千日 |
|
三十間長屋(国指定重要文化財)。 |
|
|
|
|
|
石川橋と石川門 |
|
 |
 |
|
菱櫓 |
石川門 |
 |
|
|
橋爪門続櫓 五十間長屋 菱櫓 |
|
 |
 |
|
河北門二の門 |
|
 |
 |
|
河北門一の門 |
菱櫓 |
 |
 |
|
橋爪橋 橋爪門一の門 |
|
 |
 |
|
橋爪門二の門 橋爪門続櫓 |
|
 |
|
| 戌亥櫓跡から二の丸を望む | |
 |
 |
| 極楽橋 | 三十間長屋(国指定重要文化財) |
 |
|
| 兼六園 徽軫灯籠(ことじとうろう) | |
|
|
|
 |
|
| おわら風の盆(西町コミュニティセンター) | |
 |
|
| 禅寺橋(富山市八尾) | |






