スカイツリー・浅草巡り 2017/05/30
|
義兄の手術の見舞いに2泊3日でやってきた東京。せっかく来たのだからと、中日である30日に半日の時間を割き妻が行ったことのないスカイツリーと浅草を見学することにした。混雑を避けるため早朝見学することとし、スカイツリーの入場券は、ネットでセット券(展望デッキ+展望回廊)の朝割(9:30〜10:00入館)を予約した。朝8時に宿泊先を出発、通勤通学電車のラッシュにもまれながらおよそ1時間で到着した。 |
|
 |
 |
| スカイツリー | 最高到達点(フロア450) |
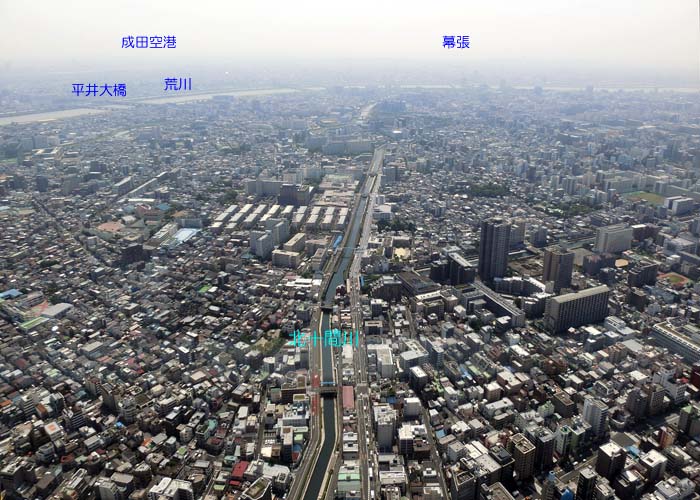 |
|
 |
|
 |
|
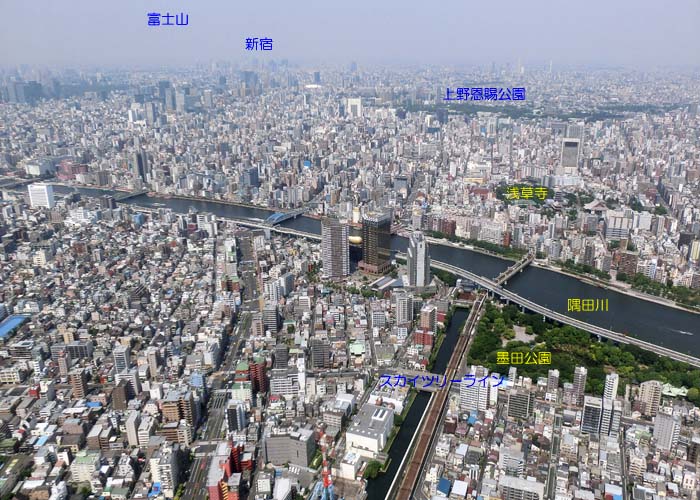 |
|
 |
|
| フロア340からの眺め | |
 |
|
| フロア350からフロア445へ向かうエレベーターにて(天井がガラス張り) | |
 |
|
| 展望回廊からの眺め | |
 |
 |
| フロア340のガラス床からの眺め | |
 |
 |
| スカイツリーライン車窓(隅田川・吾妻橋) | |
 |
|
| スカイツリー入場券 | 吾妻橋交差点にて |
|
|
|
|
|
|
| 雷神 雷門 風神 | |
 |
|
| 天龍像 雷門 金龍像 | |
 |
 |
| 大提灯 | 仲見世 |
 |
 |
| 伝法院 | 観世音菩薩像(伝法院) |
 |
 |
| 仲見世 | 常香炉 |
 |
|
| 宝蔵門(仁王門) |
|
 |
 |
| 浅草不動尊(宝光山大行院) |
浅草寺から見るスカイツリー |
 |
 |
| 五重塔 | |
 |
 |
| お水舎 | 宝篋印塔 |
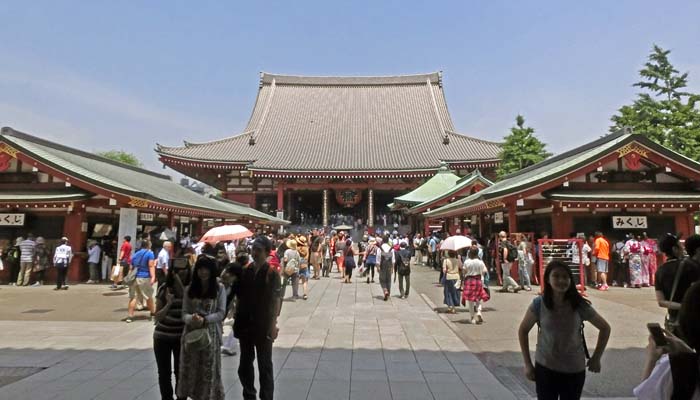 |
|
| 本堂 |
|
 |
|
| 御宮殿(本堂) |
|
 |
 |
| 阿弥陀如来像 |
讃慈雲の泉 |
|
|
|
| 浅草神社 |
|
 |
 |
| 神楽殿・舞殿 | 奥山門 |

