小豆島への旅 姫路城篇 その2 2016/11/17
|
いよいよ大天守に突入したものの、中は大変な混みようで、じっくりと見る暇がない。とにかく前へ進むしかなく、最上階への階段にいたっては身動きできない状態だった。ツアーで行っているため時間制限があり、とにかく雰囲気だけでも楽しもうと最上階を目指した。 |
|
 |
 |
|
水ノ六門から地下1階に向かう通路 |
下足番(地下1階) |
 |
|
| 姫路城下町 | |
 |
 |
|
姫路城の骨組み |
武者走り(1階) |
 |
 |
|
1階から2階へ向かう階段 |
開き窓の千鳥破風(2階) |
 |
 |
| 武者走り(2階) | |
 |
|
| 2階から3階へ向かう階段 | 東大柱(3階) |
 |
|
| 3階から4階へ向かう階段 | |
 |
 |
| 5階から4階へ下りてくる階段 | 4階から5階へ向かう階段 |
 |
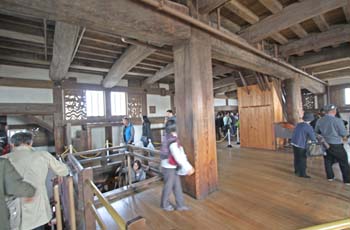 |
| 5階から最上階へ向かう階段 | 最上階 |
 |
 |
| 刑部神社 | 銅製六葉金鍍金の釘隠 |
| |
|
 |
|
| 西方面 | |
 |
|
| 北方面 | |
 |
|
| 北東方面 | |
 |
|
| 南方面 | |
 |
|
| 東方面 | |